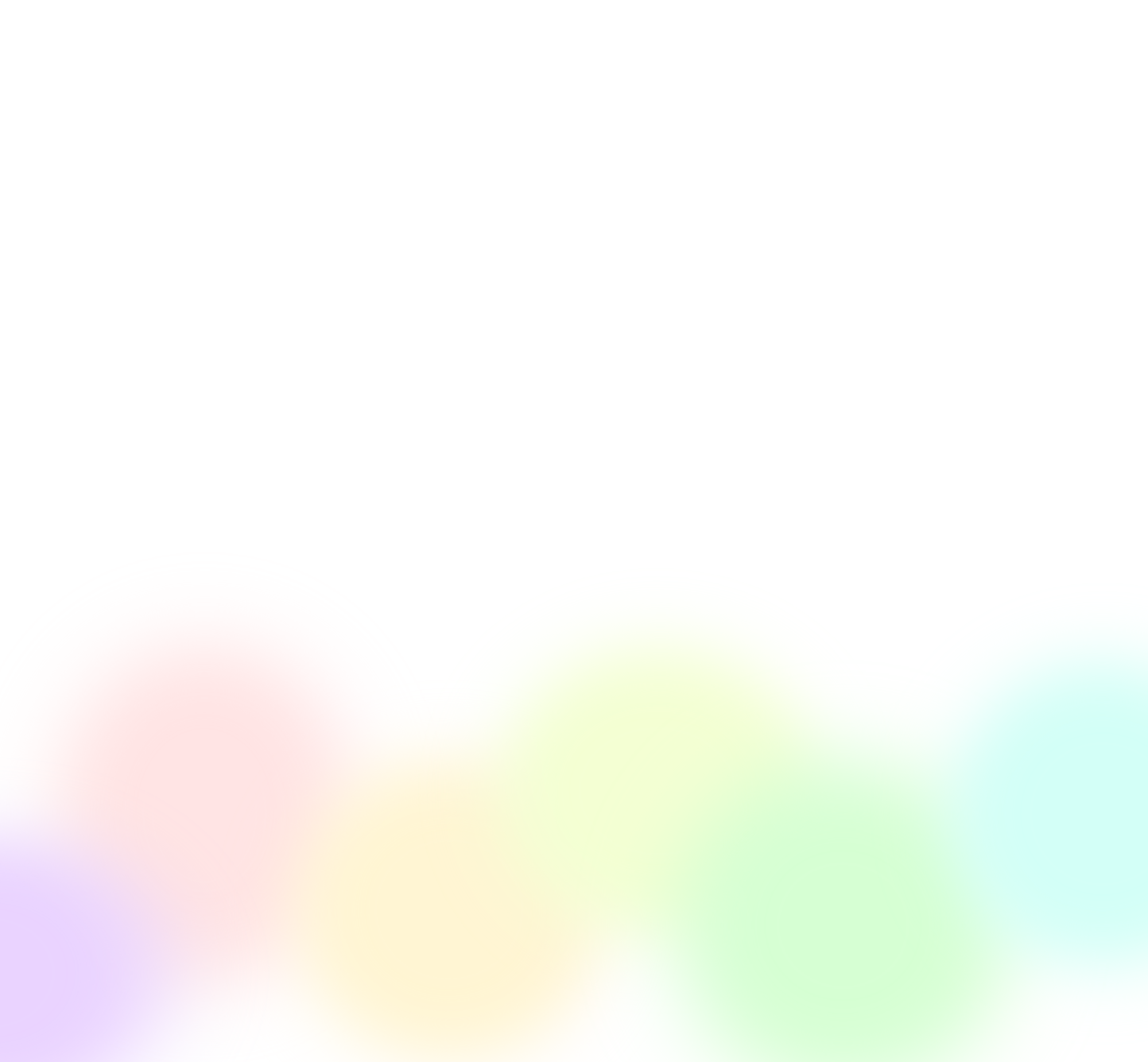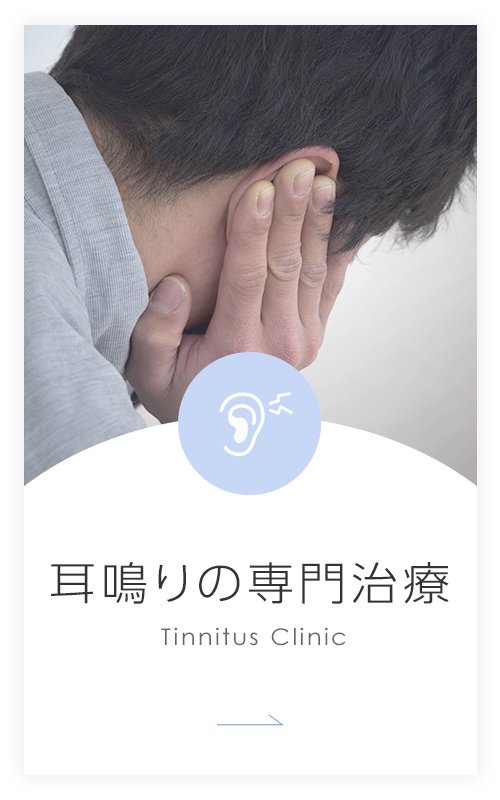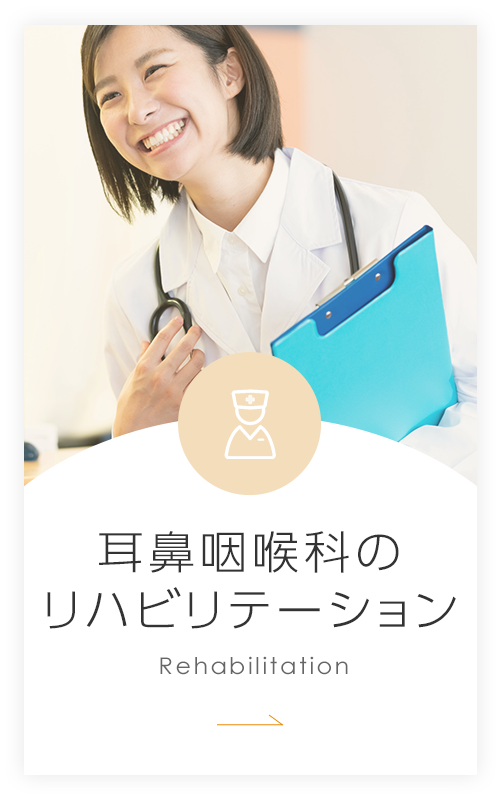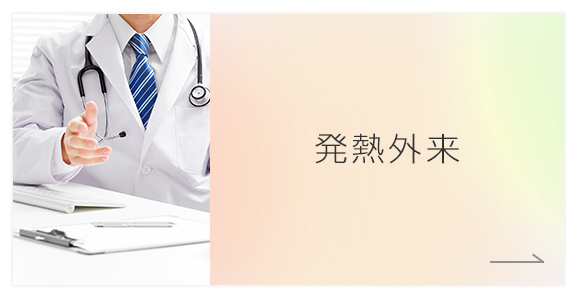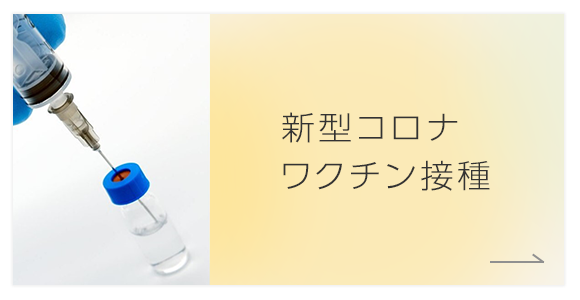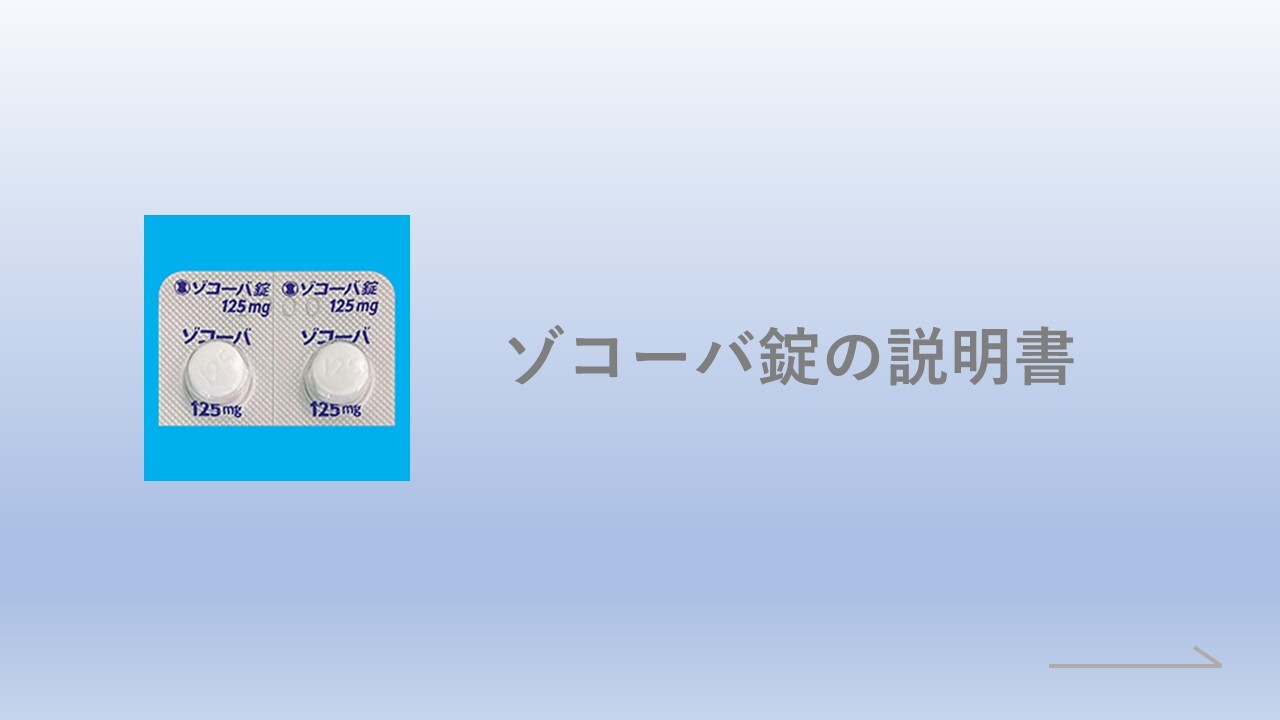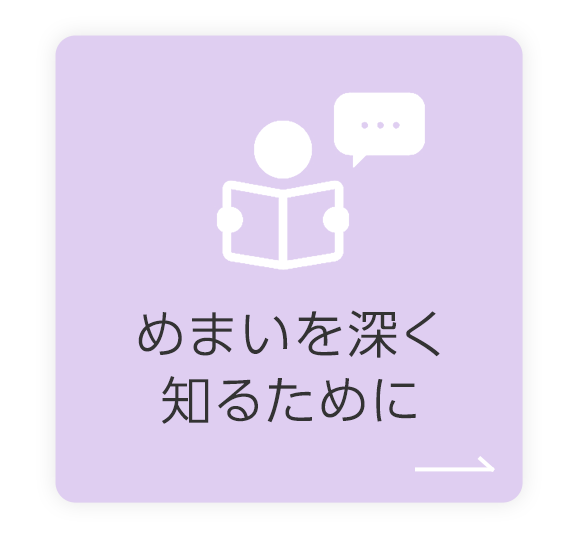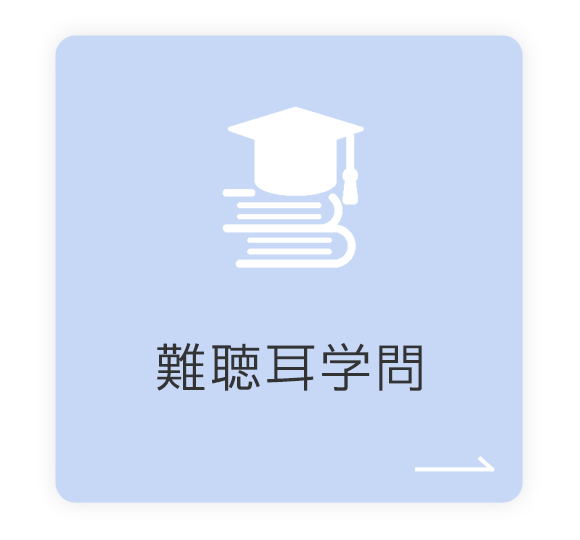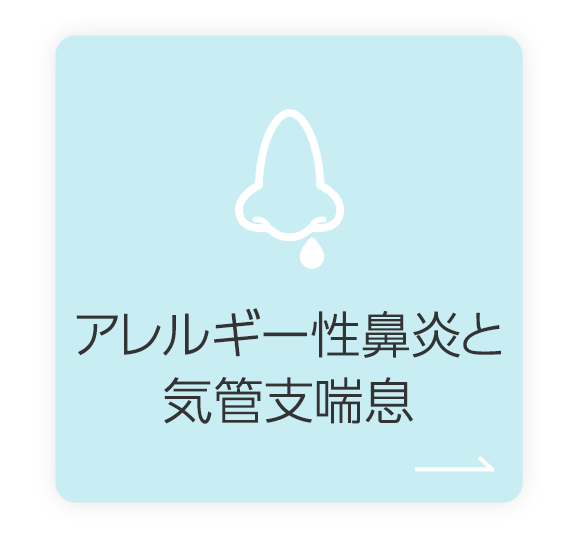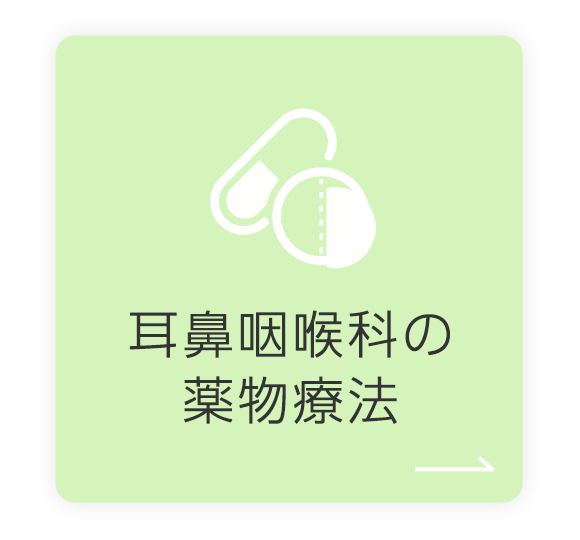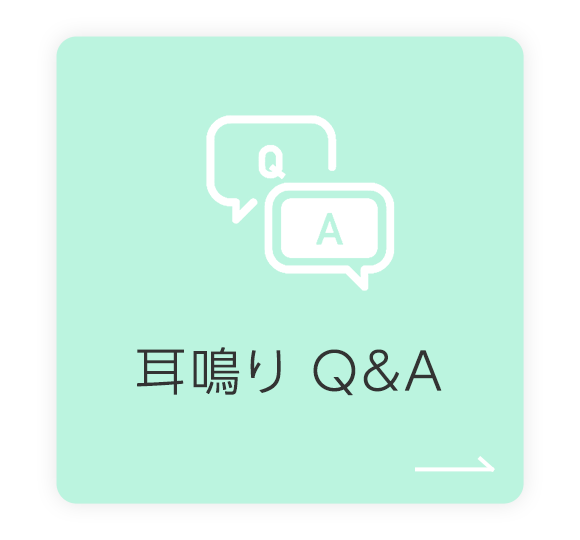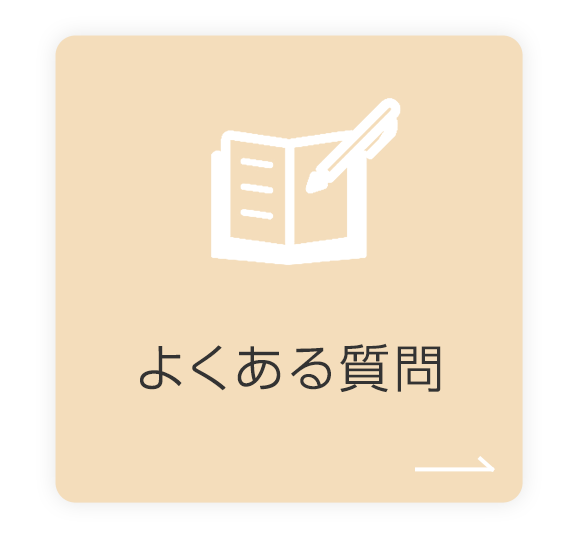――
お知らせ
News
2023.4.20 ホームページ公開
ホームページを公開いたしました。
今後とも変わらぬご愛顧をよろしくお願いいたします。
●万全な新型コロナウイルス感染症対策を実施し耳鼻咽喉科短期滞在手術を行っています。詳しくは受付にお尋ねください。
●入院のためのお時間がとれない方のための短期滞在手術を導入いたしております。
●新型コロナウイルス感染症対策のため外来受診の際には発熱・倦怠感・息切れ・嗅覚味覚障害の確認した上での外来受診をお願いたしております。
●金曜日ならびに土曜日は入院管病棟体制の状況で新型コロナ感染症の検査が行えないことがあります。あらかじめご了承ください。
――
クリニックの特長
Feature

めまいと耳鳴りの診療に注力
最新の治療理論にもとづいた、めまいと耳鳴りの総合診療を行なっています。当クリニックの院長は日本めまい平衡医学会専門会員をも務める、めまいと耳鳴りのスペシャリスト。どのようなお悩みでもご相談くださいませ。

トータルヘルスケアをご提供
耳鼻咽喉科は聴覚・平衡感覚・嗅覚・味覚などの感覚障害、呼吸機能・摂食嚥下機能など機能障害を診療する診療科です。診療する領域が多くさまざまな疾患の診療を行うことも特徴です。当クリニックでは耳鼻咽喉の病気だけではなく、その他の領域についても診療しております。

手術は日帰りから可能
適切な術前検査と術前管理、術後管理と、安定した全身麻酔により、開院以来手術は日帰り・1泊2日の短期滞在を基本としております。
――
クリニック案内
About
――
あなたの病気をより深く知るために
Column
――
診療時間・アクセス
Consultation Hours / Access
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ○ | ○ | 休 | ○ | △ | ○ | 休 |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 |
午前 9:00~12:30
午後 15:30~18:30
水曜日午前中は休診です。土曜日の診療は午前のみです。
日曜・祝祭日は休診です。
△:金曜日午前は手術のため休診となることがあります。診療可能な時間帯でのご予約は承りますのでお問い合わせください。
■所在地
〒153-0064 東京都目黒区下目黒6-18-26
■電話番号
03-3712-4970